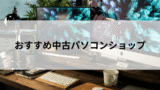「ゲーミングノートって本当にやめたほうがいいの?」「ネットで悪く言われてるけど、実際どうなの?」──PC初心者の人ほど、こんな疑問を持ちやすいですよね。調べれば調べるほど、良い意見と悪い意見が入り混じっていて、どれを信じればいいのか分からなくなるものです。
でも安心してください。最近のゲーミングノートは昔と違い、性能も使いやすさも大きく進化しています。10〜15万円前後で、モニターもキーボードも全部そろった“すぐ遊べるPC環境”が手に入るのは、初心者にとって大きな魅力です。フォートナイトやVALORANTなどの人気ゲームなら、十分すぎるほど快適に遊べるモデルも多くあります。
一方で、「発熱しやすい」「寿命が短い」「デスクトップより性能が低い」といった不安の声もよく聞きます。これらは完全に間違いではありませんが、どんな人に影響するのか、どの程度気にすべきなのかを正しく理解していないと、必要以上に怖がってしまうこともあります。
この記事では、実際にゲーミングノートを使った経験のある著者が初心者の人でも分かりやすいように、ゲーミングノートのメリット・デメリット、向いている人・向いていない人、選び方のポイントを丁寧に解説していきます。ネットの噂に振り回されず、自分に合ったPCを選べるようになるはずです。
「初めてのゲーミングPC選びで失敗したくない」「難しい話は抜きで、分かりやすく教えてほしい」という人にぴったりの内容になっています。
ゲーミングノートやめとけと言われる理由やデメリット

ゲーミングノートが「やめとけ」と言われるのは、購入後に性能面や使い勝手でギャップを感じる人が一定数いるためです。見た目はコンパクトでも、内部構造の制約からデスクトップほどの冷却性能を確保しにくく、同じ価格帯でも処理能力に差が出やすい傾向があります。
さらに、パーツ交換の自由度が低いため、長期的に性能を維持したい人にとっては不向きになりやすい点も理由のひとつです。加えて、一般的なノートPCより重量があり、バッテリーの持ちも短いため、持ち運びを前提にすると意外と不便に感じる場面もあります。こうした特徴を理解せずに選ぶと、「思っていたより使いづらい」と後悔につながる可能性があるため、慎重に検討することが大切です。
デスクトップのほうが性能が高いから
ゲーミングノートが敬遠されがちな理由のひとつに、同じ価格帯で比較した際にデスクトップのほうが高い性能を発揮しやすい点があります。ノートPCは薄型化や省スペース化が求められるため、搭載できるGPUやCPUの発熱を抑える必要があり、その結果として性能が制限されることがあります。
一方でデスクトップは大型の冷却システムを搭載でき、パーツの選択肢も豊富なため、より高い処理能力を発揮しやすい環境が整っています。特に最新ゲームを高画質で楽しみたい場合や、動画編集・3D制作など負荷の高い作業を行う場合には、この差が体感として大きく現れやすいです。こうした事情から、性能を重視するユーザーほどデスクトップを選ぶ傾向が強く、ゲーミングノートは慎重に検討すべき選択肢と考えられています。
ノートPCとデスクトップPCが同じCPU名・GPU名でも、実際の処理性能には差があります。理由は、ノートPCは電力や冷却に制限があるため、同じ型番でも性能が抑えられているためです。
CPU性能の比較
| CPU(同じ型番) | デスクトップ版の性能 | ノート版の性能 | 性能差 |
|---|---|---|---|
| Core i7(同世代) | 100% | 70〜85% | 約15〜30%低下 |
| Ryzen 7(同世代) | 100% | 75〜90% | 約10〜25%低下 |
GPU性能の比較
| GPU(同じ型番) | デスクトップ版の性能 | ノート版の性能 | 性能差 |
|---|---|---|---|
| GTX 1060 | 100% | 70〜80% | 約20〜30%低下 |
| RTX 3060 | 100% | 60〜75% | 約25〜40%低下 |
| RTX 3070 | 100% | 65〜80% | 約20〜35%低下 |
デスクトップとノートの比較
| 項目 | デスクトップPC | ノートPC |
|---|---|---|
| 処理速度 | 速い | やや遅い |
| 電力供給 | 大きい(高性能) | 小さい(制限あり) |
| 冷却性能 | 高い | 低い |
| 長時間の高負荷 | 安定 | 性能低下しやすい |
| 同じ型番のCPU/GPU性能 | 100% | 60〜85% |
同じスペック表記でも、実際の性能はデスクトップのほうが高くなりやすいです。ただし、軽いゲームや普段使いならノートPCでも十分快適に使えます。

デスクトップのほうが性能が高いのは事実ですが、ゲーミングノートでもオンラインゲームや画像編集など問題なく動作しますのでそこまで気にしなくてもよいです。
デスクトップのほうがコスパが良いから
ゲーミングノートが「やめとけ」と言われる理由の中でも、特に多くの人が挙げるのがコストパフォーマンスの差です。デスクトップは本体サイズに余裕があるため、同じ価格帯でもより高性能なパーツを搭載しやすく、結果としてゲームの快適さや処理能力に大きな差が生まれやすい傾向があります。
また、デスクトップはパーツ交換がしやすいため、必要な部分だけをアップグレードして長く使える点もコスパの良さにつながります。一方でゲーミングノートは薄型化や省スペース化のために専用設計のパーツが多く、交換できる部分が限られるため、性能を維持するためには買い替えが必要になるケースが増えがちです。
こうした違いを踏まえると、同じ予算でより高い満足度を求めるならデスクトップのほうが有利と感じる人が多いのは自然な流れと言えます。
デスクトップと違いパーツ交換が難しいから
ゲーミングノートが敬遠される理由のひとつに、パーツ交換の難しさがあります。ノートPCは薄型化や軽量化を優先した構造になっているため、内部スペースに余裕がなく、多くのパーツが基板に固定されています。
その結果、交換できるのはストレージやメモリ程度に限られ、性能を大きく向上させたい場合でも自由度が低くなりがちです。一方でデスクトップはパーツごとに独立しており、必要に応じてGPUやCPU、電源などを段階的にアップグレードできます。
この違いは長期的な使い勝手に影響し、ゲームの要求スペックが上がるたびに柔軟に対応したい人ほどデスクトップのほうが扱いやすいと感じやすくなります。こうした事情から、将来の拡張性を重視するユーザーにとってゲーミングノートは慎重に検討すべき選択肢とされています。

パーツ交換をしたい場合はデスクトップのほうが良いですが、パソコンに詳しくない初心者の方やパーツ交換の予定がない場合はゲーミングノートでも十分です。
デスクトップと違いモニターやキーボードが使いづらく本格的なゲームに向かないから
ゲーミングノートが本格的なゲームに向かないと言われる理由のひとつに、モニターやキーボードの使いづらさがあります。ノートPCは構造上、画面サイズが限られ、視認性や没入感の面でデスクトップ用の大型モニターに劣りやすい傾向があります。
また、キーボードも薄型設計が中心で、深いストロークやしっかりした押し心地を求めるゲーマーにとっては物足りなく感じることがあります。もちろん外付けのモニターやキーボードを使う方法もありますが、それではノートPCの利点である省スペース性や手軽さが薄れてしまいます。
こうした点を踏まえると、快適な操作性や高い没入感を重視するユーザーほど、デスクトップ環境のほうが満足しやすいと感じるケースが多いのです。

モニターやキーボードを別途用意しなくてもすぐに使えるというメリットもあります。
一般的なノートパソコンよりもバッテリーの駆動時間が短いから
ゲーミングノートが敬遠される理由のひとつに、バッテリー駆動時間の短さがあります。高性能なGPUやCPUを搭載しているため、通常のノートパソコンよりも消費電力が大きく、バッテリーだけで長時間ゲームを楽しむのは難しい傾向があります。
特に最新タイトルをプレイする場合、電力消費が一気に増えるため、実質的には常に電源接続が前提になることも珍しくありません。また、外出先で作業したい場合でも、バッテリーの減りが早いことで不安を感じる場面が増えやすく、持ち運び用途としては扱いづらいと感じる人もいます。
こうした特徴を理解していないと、「思ったより外で使えない」というギャップにつながりやすく、購入後の満足度に影響することがあります。

ゲーミングノートを使うタイミングは据え置きで充電しながら使うことが多いのでバッテリーの駆動時間が短くても特に気になりませんでした。
一般的なノートパソコンよりも重いため持ち運びにくいから
ゲーミングノートが敬遠される理由のひとつに、一般的なノートパソコンよりも重量がある点が挙げられます。高性能なGPUや冷却システムを搭載するため、どうしても本体が厚く重くなりやすく、カバンに入れて持ち運ぶ際に負担を感じる人が多い傾向があります。
また、電源アダプターも大型化しやすく、本体と合わせると荷物が増えてしまうため、外出先で気軽に使いたい人にとっては扱いづらさにつながります。さらに、長時間の移動や通勤・通学で持ち歩く場合、重さがストレスになりやすく、結果として「結局家でしか使わない」という状況になりがちです。
こうした点を理解していないと、購入後に持ち運びの不便さを強く感じてしまう可能性があります。

デスクトップだとそもそも持ち運びできないので好きな時に持ち運べることは大きなメリットです。
ゲーミングノートやめとけおじさんってなに?
「ゲーミングノートやめとけおじさん」とは、ゲーミングノートPCの購入を検討している人に対して、デスクトップPCのほうが良いと強く勧める人を指すネットスラングです。多くの場合、過去の経験からゲーミングノートのデメリットをよく知っており、後悔してほしくないという思いで助言しているケースが多いです。
特に性能面やコスパ、拡張性の低さなどを理由に挙げることが多く、初心者にとっては参考になる意見も含まれています。ただし、使う人のライフスタイルや目的によって最適な選択は変わるため、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。こうした背景を理解しておくことで、意見に振り回されず、自分に合ったPC選びがしやすくなります。
ゲーミングノートのメリット

ゲーミングノートには「やめとけ」と言われることがある一方で、実際には便利に使えるメリットも多くあります。特に、生活スタイルや部屋の環境によってはデスクトップよりも快適に使える場面があり、用途次第では非常に魅力的な選択肢になります。
たとえば、好きな場所でゲームを楽しめる自由度や、省スペースで設置できる手軽さは、デスクトップにはない大きな利点です。また、モニターやキーボードが一体化しているため、周辺機器を揃える必要がなく、購入後すぐにゲームを始められる点も魅力です。
さらに、外出先でもゲームや作業ができるため、趣味と仕事を両立したい人にとっては使い勝手の良いデバイスになります。こうした特徴を理解しておくことで、ゲーミングノートが自分の生活に合っているか判断しやすくなります。
寝転びながらゲームができる
ゲーミングノートの大きな魅力のひとつは、好きな姿勢でゲームを楽しめる自由度です。デスクトップのように決まった場所に座る必要がなく、ベッドやソファに寝転びながらでもプレイできるため、リラックスした状態でゲームを楽しみたい人にとっては大きなメリットになります。
また、長時間のプレイでも姿勢を変えながら遊べるため、体への負担を軽減しやすい点も魅力です。さらに、部屋のレイアウトに縛られず、気分に合わせて場所を変えられる柔軟さは、忙しい日常の中でゲームを楽しむハードルを下げてくれます。
こうした手軽さはデスクトップでは得られない特徴であり、快適さを重視するユーザーにとってゲーミングノートが選ばれる理由のひとつになっています。
スペースがない部屋でも使える
ゲーミングノートの大きな利点として、省スペースで設置できる点が挙げられます。デスクトップPCのように大きなタワーケースや外付けモニター、キーボードを置く必要がなく、机の上に本体を置くだけでゲーム環境が整います。
そのため、ワンルームや家具が多い部屋でも無理なく設置でき、生活スペースを圧迫しにくいのが魅力です。また、使わないときは簡単に片付けられるため、部屋を広く使いたい人や、作業スペースを柔軟に変えたい人にも向いています。
限られたスペースでも快適にゲームを楽しめる点は、ゲーミングノートならではの強みであり、環境に制約があるユーザーにとって大きなメリットになります。

部屋が狭かったり机が小さいとデスクトップを置きたくても置けないのでゲーミングノートは便利です。ゲームや画像編集などをしたいけど出張が多かったり、外国や引っ越しをする場合があるなどの時は良い選択肢になります。
モニターやキーボードなどの周辺機器が不要
ゲーミングノートの魅力として、購入したその日からすぐにゲームを始められる手軽さがあります。デスクトップPCのように外付けモニターやキーボード、スピーカーなどを揃える必要がなく、本体だけでゲーム環境が完結するため、初期準備の手間が大幅に減ります。
また、周辺機器を置くスペースを確保する必要がないため、机が狭い部屋や家具が多い環境でも快適に使える点もメリットです。さらに、配線が少なく済むことでデスク周りがすっきりし、掃除やレイアウト変更もしやすくなります。こうした手軽さは、ゲーム初心者や機材を増やしたくない人にとって大きな利点となり、ゲーミングノートを選ぶ理由のひとつになっています。

既にゲーミングデスクを所有している方は、モニターやキーボードは既にあり別途用意する必要はないです。ただ、初心者や何も持っていない方にとってゲーミングノート一つ買えばすぐに使えるのは大きなメリットです。
持ち運んで使える
ゲーミングノートの大きな魅力として、場所を選ばずに使える携帯性があります。デスクトップのように固定された環境を必要とせず、カフェや実家、旅行先など、好きな場所に持ち運んでゲームや作業ができる点は大きな利点です。
特に、仕事や学業で外出が多い人にとっては、1台でゲームも作業もこなせる柔軟さが便利に感じられます。また、LANパーティーや友人宅でのゲーム会など、機材を持ち寄る場面でもノートPCなら手軽に参加できます。こうした自由度の高さは、生活スタイルに合わせて使い方を変えたい人にとって大きなメリットとなり、ゲーミングノートが選ばれる理由のひとつになっています。

外でゲームや画像編集ができるのはもちろん、家の中でも机やベッドなど好きな場所に持ち運んで使えるのはゲーミングノートの強みです。
ゲーミングノートPCを普段使いするのはあり?

ゲーミングノートPCを普段使いするのは十分に選択肢として成立します。高性能なCPUやGPUを搭載しているため、ブラウジングや動画視聴はもちろん、画像編集や資料作成などの作業も快適にこなせます。
特に、動作の軽快さを重視する人にとっては、一般的なノートPCよりもストレスの少ない環境を得られる点が魅力です。また、処理能力に余裕があることで、複数のアプリを同時に開いても動作が重くなりにくく、日常的な作業の効率が上がりやすいというメリットもあります。
一方で、重量やバッテリー持ちなど、携帯性の面では一般的なノートPCに劣る部分もあるため、外出先での使用が多い人は注意が必要です。こうした特徴を踏まえると、普段使いを快適にしたい人にとってゲーミングノートは十分「あり」と言える選択肢になります。

ゲーミングノートはスペックが高いので普段使いでもスムーズに滑らかに動くので快適に使えますよ。
ゲーミングノートPCは後悔する?
ゲーミングノートPCで後悔するかどうかは、使う人の目的や環境によって大きく変わります。たとえば、高画質で最新ゲームを長時間プレイしたい場合や、将来的にパーツを交換しながら長く使いたい場合には、デスクトップのほうが満足度が高くなりやすい傾向があります。
そのため、ゲーミングノートを選ぶと「思ったより性能が伸びない」「熱が気になる」と感じて後悔につながるケースがあります。一方で、好きな場所でゲームを楽しみたい人や、省スペースで使いたい人にとっては、ゲーミングノートの利便性が大きな魅力になります。
持ち運びができることや、周辺機器を揃えなくてもすぐに使える点は、デスクトップにはない強みです。こうした特徴を理解したうえで、自分の使い方に合っているかを判断すれば、後悔を避けやすくなります。

ゲーミングノートを使って後悔したことはないです。
ゲーミングノートPCは情弱向け?
ゲーミングノートPCが「情弱向け」と言われることがありますが、これは一部の意見に過ぎず、実際には使う人の目的や環境によって評価が大きく変わります。
たしかに、デスクトップと比べると性能や拡張性で不利になる場面があり、その点だけを基準にすると「詳しい人は選ばない」というイメージが生まれやすいのは事実です。
しかし、持ち運びができることや、省スペースで使える手軽さはゲーミングノートならではの強みであり、ライフスタイルに合っていれば十分に合理的な選択になります。また、最近のモデルは性能も向上しており、ゲームだけでなくクリエイティブ作業や普段使いにも対応できる柔軟さがあります。重要なのは、他人の評価ではなく、自分の用途に合っているかどうかを基準に選ぶことです。

情弱向けパソコンではありません。今回の記事で紹介する内容を踏まえて納得して購入すればむしろ最適な選択肢になりえます。
ゲーミングノートの選び方

ゲーミングノートを選ぶ際は、まず自分の用途に合った性能や機能を見極めることが大切です。ゲームの種類や作業内容によって必要なスペックは大きく変わるため、目的を明確にすることで無駄な出費を避けられます。
また、ノートPCはデスクトップに比べてパーツ交換が難しいため、購入時のスペック選びがとても重要になります。さらに、持ち運びの頻度や設置スペースなど、ライフスタイルに合わせた選び方をすることで、購入後の満足度が高まりやすくなります。こうしたポイントを押さえておくことで、自分に最適なゲーミングノートを選びやすくなり、長く快適に使える環境を整えられます。
そもそもグラボが必要な用途か確認する
ゲーミングノートを選ぶ前に、まず自分の用途に本当にグラフィックボード(GPU)が必要かどうかを確認することが重要です。最新ゲームや3D制作、動画編集、AI処理など、GPUの性能が直接作業効率に影響する用途であれば、ゲーミングノートは大きな力を発揮します。
しかし、ブラウジングやOffice作業、動画視聴といった軽い用途が中心であれば、必ずしも高性能GPUは必要ありません。むしろ、GPUを搭載しない一般的なノートPCのほうが軽量でバッテリー持ちも良く、コストも抑えられます。自分がどの程度の性能を求めているのかを明確にすることで、無駄な出費を避けつつ、最適なPC選びができるようになります。
目的のゲームやソフトがあれば推奨要件を確認する
ゲーミングノートを選ぶ際には、プレイしたいゲームや使用したいソフトの「推奨要件」を必ず確認することが重要です。必要スペックを満たしていないと、カクつきやフリーズが発生し、快適にプレイできない可能性があります。
特に最新の3Dゲームや動画編集ソフト、AI処理を行うアプリはGPU性能が大きく影響するため、推奨要件を基準にスペックを選ぶことで失敗を避けられます。
また、推奨要件はあくまで“快適に動かすための最低ライン”であり、長く使うことを考えるなら少し余裕を持ったスペックを選ぶのが安心です。事前に必要性能を把握しておくことで、購入後に「思ったより動かない」という後悔を防ぎやすくなります。
おすすめゲーミングノートPC
ゲーミングノートPCを選ぶ際は、性能・価格・携帯性のバランスが重要です。ここでは、初心者から中級者まで扱いやすく、コスパの良いモデルを選ぶ際の基準を踏まえつつ、どんなタイプのゲーミングノートが「おすすめ」と言えるのかを整理します。具体的なモデル名は市場の変動が大きいため、ここでは“選ぶべきスペックの方向性”を中心に紹介します。
Lenovo Legion 5i Gen 10 – エクリプスブラック
おすすめゲーミングノートパソコンはLenovo Legion 5i Gen 10 – エクリプスブラックです。十分なスペックはありつつも価格は抑えておりコスパに優れたゲーミングノートです。スペックを求められるオンラインゲームも問題なく動作します。
中古ゲーミングノートもおすすめ
最近はメモリ価格高騰の影響を受けゲーミングノートパソコンの価格も上昇傾向にあります。ゲーミングノートパソコンが欲しいけど高いから買えないという方は中古パソコンショップで購入するのもおすすめです。
パソコンのスペックは年々上昇しており、中古ゲーミングノートでも十分なスペックがあります。中古パソコン探している方におすすめな中古パソコンショップはQualitです。商品の質が高くバッテリーテスト結果80%以上を保証しているショップなので、中古パソコンをお探しならチェックしてみてください。
ゲーミングノートPCは何年で買い替え?

ゲーミングノートPCの買い替えタイミングは、一般的に3〜5年が目安とされています。理由としては、ノートPCはデスクトップに比べてパーツ交換が難しく、経年による性能不足や熱による劣化が起きやすいためです。特にGPU性能の進化は早く、最新ゲームを快適に遊び続けたい場合は、3年ほどでスペック不足を感じるケースもあります。
一方で、軽めのゲームや普段使いが中心であれば、5年以上使い続けることも十分可能です。実際には、「どのゲームをどの設定で遊びたいか」や、「どれだけ持ち運ぶか」など、使い方によって寿命は大きく変わります。また、バッテリーの劣化や冷却性能の低下が気になり始めたら、買い替えのサインと考えてよいでしょう。
長く使いたい場合は、購入時に少し余裕のあるスペックを選ぶことが重要です。特にGPU・CPU・冷却性能がしっかりしたモデルを選べば、寿命を伸ばしやすくなります。
ゲーミングノートでよく言われる、デスクトップよりも排熱されにくく熱により劣化しやすいということがありますが、そんな方はPCクーラーの使用をおすすめします。熱による寿命の劣化を抑えることができます。

サンワダイレクト ノートパソコンクーラー 冷却台 アルミ 15.6インチ対応 静音 角度8段階 風量無段階 USB2ポート USB給電 400-CLN031
ゲーミングデスクトップとノートどっちがいい?
ゲーミングPCを選ぶ際に多くの人が悩むのが、「デスクトップとノートのどちらが自分に合っているのか」という点です。どちらにも明確なメリットとデメリットがあり、最適な選択はライフスタイルや用途によって大きく変わります。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、どんな人にどちらが向いているのかを整理します。
性能重視ならデスクトップが有利
デスクトップは冷却性能に余裕があり、同じ価格帯でもノートより高いパフォーマンスを発揮しやすいのが特徴です。最新ゲームを高画質で長時間プレイしたい人や、将来的にパーツを交換しながら長く使いたい人にはデスクトップが向いています。
手軽さ・省スペース性ならノートが便利
一方で、設置スペースが限られている場合や、好きな場所でゲームを楽しみたい人にはゲーミングノートが最適です。モニターやキーボードが一体化しているため、購入後すぐに使える手軽さも魅力です。
持ち運びが必要ならノート一択
外出先でもゲームや作業をしたい、実家や友人宅にPCを持っていく機会がある、という人にはノートが圧倒的に便利です。デスクトップは基本的に据え置き前提のため、移動には向きません。
コスパはデスクトップが優勢
同じ価格帯で比較すると、デスクトップのほうが高性能なパーツを搭載できるため、コストパフォーマンスはデスクトップが有利です。長期的に見ても、パーツ交換で性能を維持できる点は大きなメリットです。
静音性・熱対策はデスクトップが有利
ノートは内部スペースが限られているため、どうしても熱がこもりやすく、ファンが高回転になりがちです。静音性や安定した冷却を求めるならデスクトップが適しています。
結論:用途と環境で選ぶのが正解
性能・コスパ・拡張性を重視するならデスクトップ、
手軽さ・省スペース・持ち運びを重視するならノートが最適です。 どちらが優れているかではなく、「自分の使い方に合っているか」が最も重要なポイントです。
まとめ

ゲーミングノートPCは、デスクトップにはない手軽さ・省スペース性・持ち運びの自由といった大きな魅力を持つ一方で、性能・拡張性・冷却面ではデスクトップに劣る部分があります。そのため、「どちらが優れているか」ではなく、自分の用途・環境・優先したいポイントによって最適な選択が変わります。
普段使いもゲームも1台でこなしたい、好きな場所でプレイしたい、省スペースで使いたいという人にはゲーミングノートが最適です。一方で、高性能を求める、長く使いたい、パーツ交換でアップグレードしたいという人にはデスクトップが向いています。
この記事で紹介したメリット・デメリット、選び方のポイントを踏まえて、自分のライフスタイルに合ったゲーミングPCを選べば、後悔のない満足度の高い買い物ができるはずです。